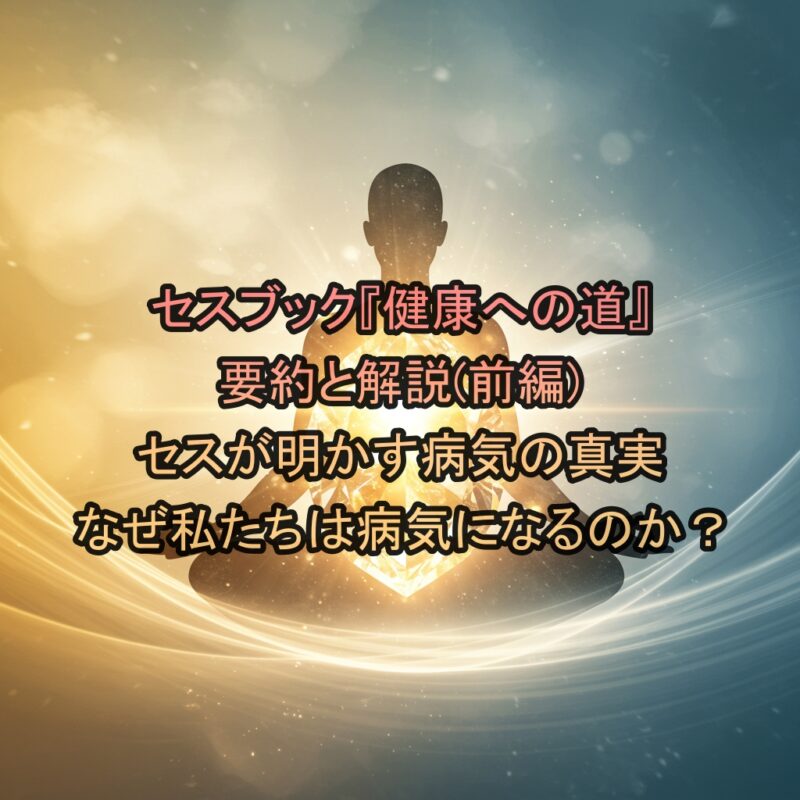私たちは不調を感じると、その原因をウイルスや不運など「外側」に求め、自らを無力な被害者だと考えがちです。
しかし、もし病気の本当の原因が、私たち自身の「内なる世界」にあるとしたらどうでしょう。
高次元存在セスが語る『健康への道』は、その常識を覆す洞察を与えます。
驚くべきことに、チャネラーのジェーン・ロバーツは、自身が重病で身体の自由を失った状態でこの本を執筆しました。
セスによれば、病気とは偶然ではなく、私たちの意志の葛藤や心の奥底にある「信念」、そして未表現の感情が、身体というスクリーンに映し出されたメッセージなのです。
この記事では、セスブックの叡智を基に、なぜ私たちが自ら不調を「選択」してしまうのか、その深層心理を解き明かします。
病気の「被害者」から健康の「創造主」へ。その第一歩となる真実を探っていきます。

本記事のラジオ形式の音声版をご用意いたしました。
文章を読む時間がない時や、リラックスしながら内容を深く味わいたい時などにご活用いただければ幸いです。
生きる意志と「病気になる意志」の葛藤
私たちの存在の根底には、あらゆる生命に共通する、生きようとする根源的な衝動、**「生きる意志」**が力強く流れています。
それは単なる生存本能ではなく、成長し、発展し、喜びを体験しようとする、創造性に満たた宇宙的な力です。
花が太陽に向かって咲き、鳥が空を舞うように、私たちの魂もまた、自己を表現し、人生という舞台で輝くことを本質的に望んでいます。
しかし、セスによれば、私たちは時に、この偉大な力と矛盾する願望を抱いてしまうことがあると言います。

矛盾した願望:なぜ自ら不調を「選択」するのか
「生きたい」と心から願いながらも、同時に「人生の困難から隠れたい」「これ以上傷つきたくないから安全な場所にいたい」と感じることはないでしょうか。
この一見些細に見える心の葛藤が、実は私たちの進歩を妨げ、身体の動きを無意識に制限する大きな力となり得ます。
それはまるで、一台の車でアクセルとブレーキを同時に踏み込んでいるような状態です。
エネルギーは激しく消費される一方で、車は一向に前へ進まず、やがてエンジン(身体)に深刻な不調をきたすのです。
この状態にあるとき、私たちは前に進みたいという願望と、その先に待つかもしれない未知の恐怖との間で引き裂かれています。
この内なる摩擦は、精神的な疲弊だけでなく、具体的な身体症状として現れます。
例えば、新しいプロジェクトに挑戦したいという情熱(アクセル)と、失敗するかもしれないという恐れ(ブレーキ)が同時に働けば、重要なプレゼンテーションの前に決まって激しい頭痛が起きるかもしれません。
それは、「進みたいけれど進みたくない」という心の叫びが、身体を通して発せられたサインなのです。
セスは、このような矛盾した思いが、私たちの生命エネルギーそのものへの不信感から生まれると指摘します。
自分自身のエネルギーの性質を懸念し、それが自分を破壊するのではないかと恐れているのです。言い換えれば、彼らは自分自身の生命のエネルギーを信頼していないのです。
―セス
自分の中に眠る自発性(心のままに行動する力)や冒険心(未知へと踏み出す勇気)といったパワフルな生命力。
それは、大それた挑戦だけでなく、日常の些細な場面、例えば「本当の気持ちを伝える」「新しい趣味を始める」「慣れた道を外れてみる」といった行動にも現れます。
これらの行動は、私たちの魂が持つ自然な輝きであり、人生を豊かに彩るための衝動です。
しかし、もし幼少期にそのような自発的な行動が親や教師から罰せられたり、「わがままだ」「変わっている」と嘲笑されたりした経験があれば、私たちは「ありのままの自分を表現することは危険であり、愛されない原因になる」と深く学習してしまいます。
子供にとって、所属する集団(特に家族)からの承認は、生き残るための絶対条件です。
そのため、私たちは自らの自然な衝動を抑え込み、周囲が期待する「良い子」の仮面を被ることを覚えます。
その結果、自らの内なる衝動を信頼し、解放することを恐れるようになり、私たちは自らそのエネルギーの流れを堰き止め、短絡させてしまうのです。
堰き止められたエネルギーは消えてなくなるわけではなく、行き場を失い、内側で渦巻きます。
その結果が、原因不明の慢性疲労や自己免疫疾患、アレルギー、運動機能の制限、あるいは人間関係における自己破壊的なパターン、さらには深刻な事故といった形で、私たちの現実に現れるのです。
現実を創造する「信念」という設計図
では、なぜ私たちは自らの生命力を恐れてしまうのでしょうか?
その答えは、バシャールもよく言っている私たちの最も深いレベルで保持している**「信念(Belief)」**に隠されています。
それは、私たちが意識しているかどうかに関わらず、私たちの現実を形作るための「設計図」として機能しています。
信念とは単なる一時的な思考ではありません。
それは、経験や教育を通じて深く刻み込まれ、感情と一体化した、世界の捉え方そのものです。
セスは、私たちの身体は、自らが抱く信念を忠実に映し出す鏡であると語ります。
思考や感情はもちろんのこと、健康状態という物理的な現実までもが、この信念という設計図に基づいて創造されているのです。
どんなに健康的な食事や運動を心がけても、設計図自体が「自分は病弱である」「自分は幸せになる価値がない」といった歪んだものであれば、現実はその通りに建設されてしまうでしょう。
意識の上では健康を望んでいても、潜在意識レベルの設計図がそれを許可しない限り、身体は正直にその設計図に従い続けるのです。
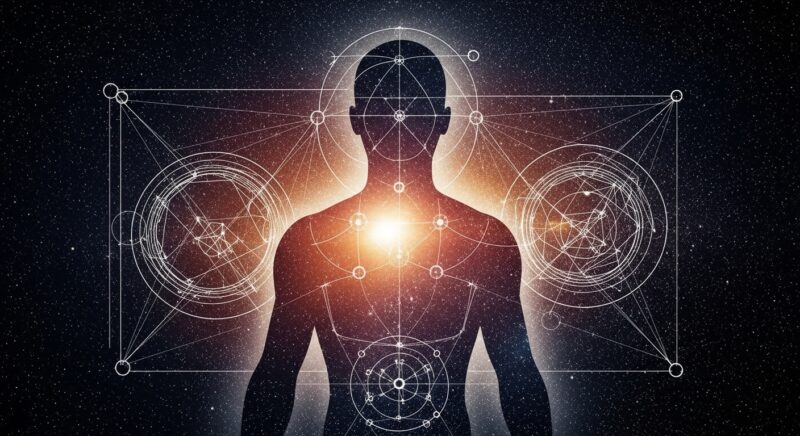
社会通念という名の”呪い”
特に根深い影響を持つのが、私たちが無意識のうちに取り込んでいる社会的な信念です。
これらは文化や家庭環境を通じて、まるで空気のように私たちの内面に浸透し、個人の信念体系の基盤となります。
これらの信念は非常に巧妙で、多くの場合、社会的な美徳や常識として私たちの前に現れるため、その有害性に気づくことは困難です。
- 「才能のある者は、他者から嫉妬され、攻撃される」:
この信念は、「出る杭は打たれる」という文化的な格言に象徴されます。
この信念を持つ人は、成功を目前にすると原因不明の体調不良に見舞われたり、大事な場面で力を発揮できなくなったりします。
これは無意識の自己防衛メカニズムです。
病気になることで、他者からの嫉妬という「危険」から身を守り、「あの人は才能があるけれど、体が弱いから仕方ない」という同情を得て、安全な場所に留まろうとするのです。
成功への道を自ら閉ざすことで、人間関係の調和を保とうとする、悲しいほどの自己犠牲とも言えます。 - 「目立つ行動をとるべきではない」:
自己主張をすると、仲間外れにされるかもしれないという、集団からの孤立への根源的な恐れ。
これが、声が出なくなる、喉に不調をきたす、あるいは人前に出ると極度に緊張して汗が止まらないといった症状に繋がることがあります。
文字通り、自分の「声」を出すこと、自分の存在を「示す」ことを物理的に妨げるのです。
これは、自分の意見が全体の調和を乱すかもしれないという罪悪感と深く結びついています。 - 「常に謙虚でいなければならない」:
これは美徳とされますが、行き過ぎると自己肯定感の欠如に繋がります。
自分の功績を素直に喜べず、常に自己評価を低く保とうとする姿勢は、生命の自然な輝きや喜びを抑圧します。
これが、猫背やうつむきがちな姿勢となって身体に現れ、慢性的な首や肩の凝り、呼吸の浅さを引き起こす可能性があります。
身体が縮こまることで、心もまた内向きになり、生命エネルギーの循環が滞ってしまうのです。 - 「成功のためには、血の滲むような努力と犠牲が不可欠だ」:
「楽して手に入れたものに価値はない」という信念。
楽しんで何かを成し遂げることに罪悪感を抱き、常に自分を追い込み、苦しみを伴わない成功を無意識に拒絶します。
リラックスすることができず、自律神経のバランスを崩したり、過労からくる様々な不調を招いたりします。
この信念は、人生が闘いであるという世界観を強化し、身体を常に臨戦態勢に置くため、心身が休まる時がありません。 - 「男は弱音を吐くべきではない」「女は自己犠牲的であるべきだ」:
性別による固定観念は、自然な感情表現を妨げる最も強力な”呪い”の一つです。
男性は悲しみや不安といった感情を抑圧し、怒りや攻撃性としてしか表現できないことがあります。
泣きたいときに泣けず、溜め込まれた感情の圧力が、高血圧や心臓疾患として爆発することがあります。
一方、女性は自分のニーズを後回しにし、他者のために尽くすことが美徳とされる文化の中で、慢性的な疲労や婦人科系の問題、自己免疫疾患などを発症することがあります。
このような社会に深く根差した信念は、私たちの自己表現への道を塞ぎ、生命エネルギーの流れを歪めます。
そして、自分の持つ素晴らしい才能やユニークさを表現することに罪悪感や恐れを抱かせ、無意識のうちに「自分自身を罰する」ためのハンディキャップとして、あるいは「自分らしく生きられない」という魂の叫びとして、病気を創り出してしまうことがあるのです。
症状に隠された信念のメッセージ
セスは、具体的な症状と、その背後にある信念との関連性についても鋭い洞察を示しています。
症状は、私たちの身体が送る比喩的なメッセージであり、内なる不調和を知らせる警報なのです。
- てんかん:
自分自身のエネルギーが他者を傷つけるかもしれないという強い恐れから、その莫大なエネルギーを一気に放電させ、一時的に自分を無力化(ショート)させる行為。それは、コントロール不能な力に対する究極の自己防衛なのです。 - 吃音(どもり):
てんかんと同様に、完璧主義的な傾向や、自分の力強い自己表現への恐れが、言葉という形で「ぎくしゃくした」不均一な身体的振る舞いとして現れたもの。 - 多重人格:
自己のエネルギーを恐れるあまり、それを複数の人格に分割し、本来の自分が持つ全ての力を使えないようにする心理的な戦略。
これにより、「良い自分」は社会的な自分を保ちつつ、「悪い自分」に抑圧された衝動を表現させることができるのです。 - 関節炎などの運動障害:
自発的な行動や感情表現への恐れが、身体の「動き」そのものを制限する形で現れたもの。
関節の痛みや硬直は、心理的な頑固さや、過去の怒り・恨みを「手放せない」でいる心の状態を物理的に反映しているのかもしれません。 - 心臓疾患:
文字通り「心が張り裂ける」ような悲しみや、「人生への情熱(heart)を失った」という感覚の現れ。
また、自分は「冷酷(heartless)だ」という自己非難が、自らを罰するために心臓を攻撃することもあります。
愛を与えたり受け取ったりすることへの恐れが、血流という生命の循環を滞らせるのです。 - 胃潰瘍:
特定の状況や感情を「消化できない」「受け入れがたい」という強い抵抗感の象徴。
怒りや不安、心配事などを溜め込み、文字通り胃に穴をあけてしまうのです。 - 癌:
長い間抱えてきた深い悲しみ、恨み、あるいは「生きる意味がない」という絶望感が、特定の身体部位で増殖し始めたもの。
自己の創造的なエネルギーが健全な形で表現される道を塞がれ、破壊的な形で内側に向かってしまった状態とも言えます。 - 便秘や水分の滞留:
セクシュアリティや権力といった、自らの強い衝動を「抑圧」していることの現れ。
手放すことへの恐れが、身体的なレベルでの「溜め込み」として象徴的に表現されます。 - エイズ:
社会的な偏見に直面した特定の集団が抱く、深い無力感や自己嫌悪、そして「生きる意志」の衰弱が引き起こす、いわば「生物学的な抗議」。これは社会的な現象としての側面も持ちます。
これらの症状はすべて、**「自分自身の力やエネルギーは危険である」**という、歪んだ信念から生まれる自己防衛の現れなのです。一見すると全く異なるこれらの不調も、その根源をたどれば、自己の神聖な力を誤解し、恐れてしまったという一点に集約されるのです。
まとめ:病気の創造主はあなた自身
ここまで見てきたように、セスが示す病気のメカニズムは、それが決して外部からやってくるものではないことを明らかにしています。
病気とは、私たちの**「生きる意志」と「人生への恐れ」との葛藤**、そして**「自己の力は危険である」というネガティブな信念**が、複雑に絡み合って創り出した、私たち自身の創造物なのです。
この事実は、一見すると厳しいものに感じられるかもしれません。
しかし、ここには大いなる希望が隠されています。
もし病気の原因が自分自身の内にあるのなら、それを変える力もまた、自分自身の内に秘められているということです。
次回の記事では、この仕組みを理解した上で、私たちに本来備わっている偉大な自己治癒力を目覚めさせ、真の健康への道を取り戻すための具体的な方法と、より大きな視点について、さらに深く探求していきます。
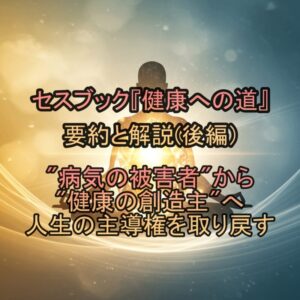
このブログを読んで、さらに見識を深めたいと思ったらぜひ本書を手に取ってみてください。
本書は日本語版はまだ発売されてなく英語版のみとなります。